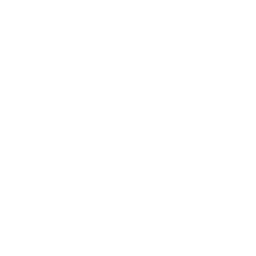2024.07.29
酸素と二酸化炭素の交換
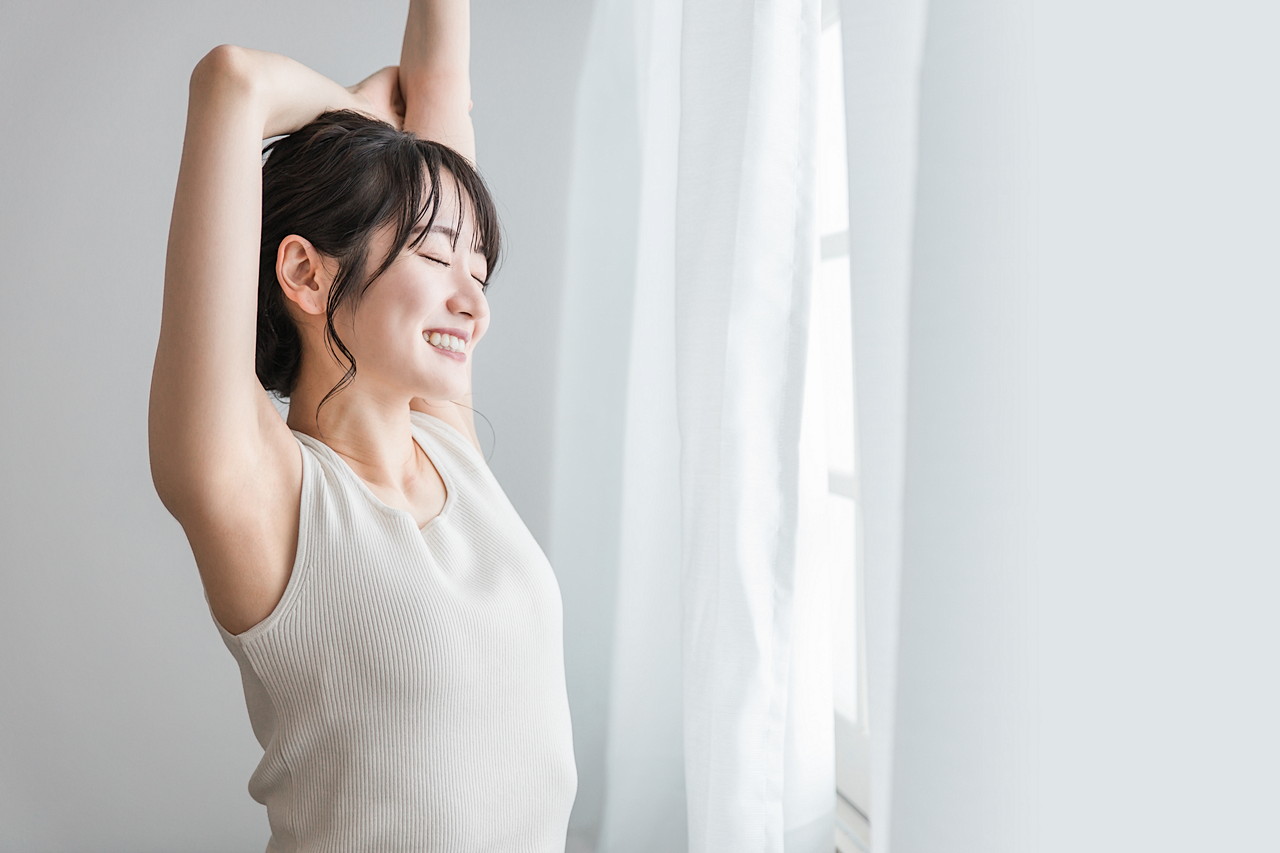
日々繰り返される呼吸。
呼吸によって酸素と二酸化炭素の交換が
行われます。
この交換は一見複雑そうに思えますが
基本的な原理が利用されています。
今回は酸素・二酸化炭素が
体内でどのように交換されていくかを
解説いたします。
目次
Contents
目次
Contents
1.拡散と分圧
酸素が体内で交換される仕組みには
”拡散”と”分圧”が深くかかわります。
拡散も分圧も
高い(濃い)方から
↓
低い(薄い)方へ
物質が移動します。
2.酸素、二酸化炭素分圧
- 肺胞
- 細胞
- 静脈血
- 静脈血
それぞれの酸素・二酸化炭素分圧の違いが
体内での酸素・二酸化炭素の交換に
役立っています。
動脈と静脈
まず、動脈と静脈の大まかな違いについて
◎動脈
心臓から全身へ”出ていく”血管
身体の各所へ酸素を運搬する
◎静脈
全身をめぐって心臓へ”戻る”血管
二酸化炭素分圧が高い
肺胞
肺を構成する”ぶどう”のような器官
呼吸をすると
吸った空気は気管を通って
まず肺へ運ばれます。
この吸った”空気”は酸素をたくさん含んで
いるので肺胞の酸素分圧は高くなります。
それに比べ全身から戻ってきた
静脈の中の静脈血は酸素分圧が低い
状態になっています。
分圧は高→低へ物質が移動するため
ここでは肺胞→静脈血への酸素の交換が
行われます。
そしてその静脈が心臓へ戻り
動脈から全身の細胞へ回っていきます。
動脈の中を通る動脈血は
酸素を十分に含んでおり
酸素分圧は”高い”状態です。
そして、各細胞へとめぐっていきますが
その各細胞は、エネルギーを産生するのに
酸素を使用しているため
酸素分圧は動脈血と比べて低い状態にあります。
そのことにより
動脈血の酸素は各細胞へ交換されます。
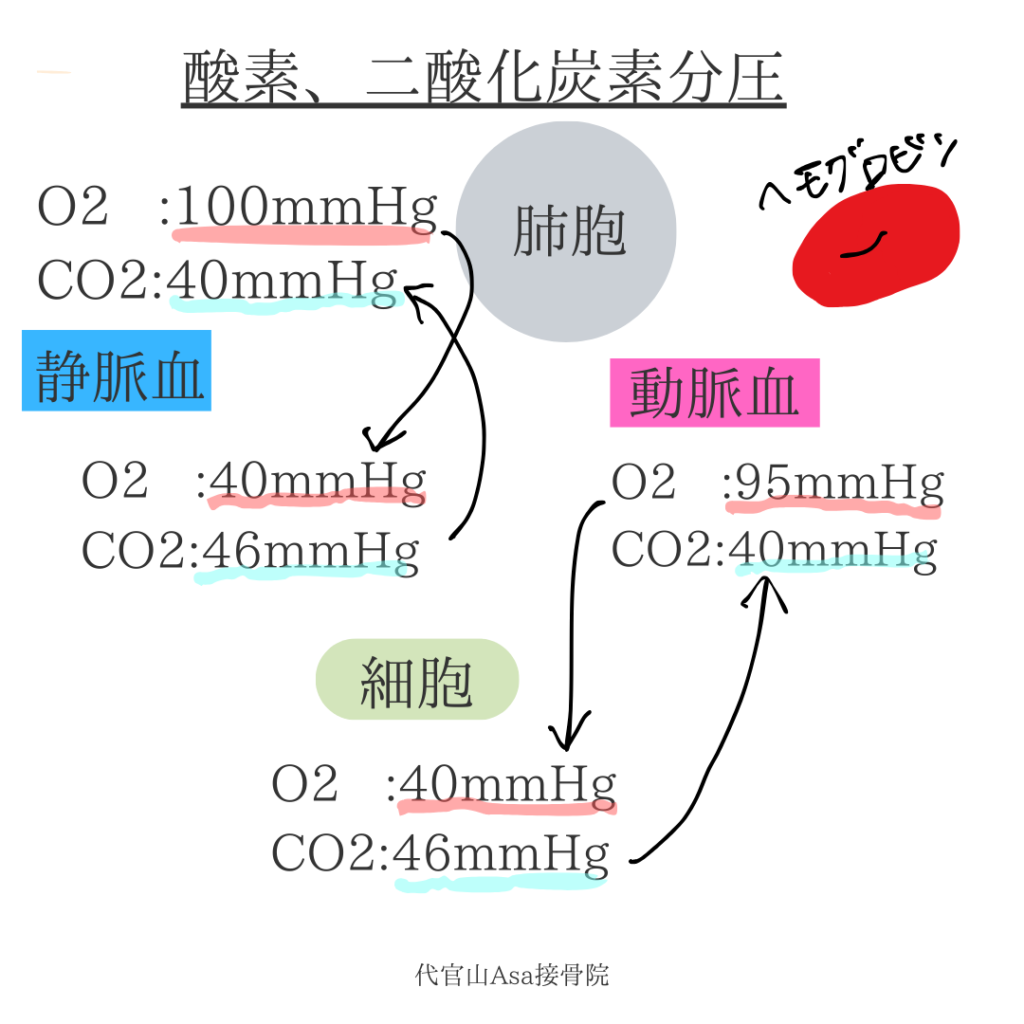
3.酸素交換にたいせつなヘモグロビン
酸素の運搬に欠かせないのが
”ヘモグロビン”
このヘモグロビンは動脈血に多く含まれ
酸素の運搬が重要な役割の一つです。
このヘモグロビンの特徴的として
”酸素の多いところでは酸素と結合しやすく
酸素の少ないところでは酸素を離しやすい”
という性質があります。
吸った酸素をしっかりと
体内の細胞へ送るためには
”ヘモグロビンが酸素を解離する”ことが
重要になります。
では、どういった状態が
酸素を解離しやすい状態になるのかを
次回の投稿で解説していきたいと思います。
女性のための代官山Asa接骨院
\ ご予約はこちらから /